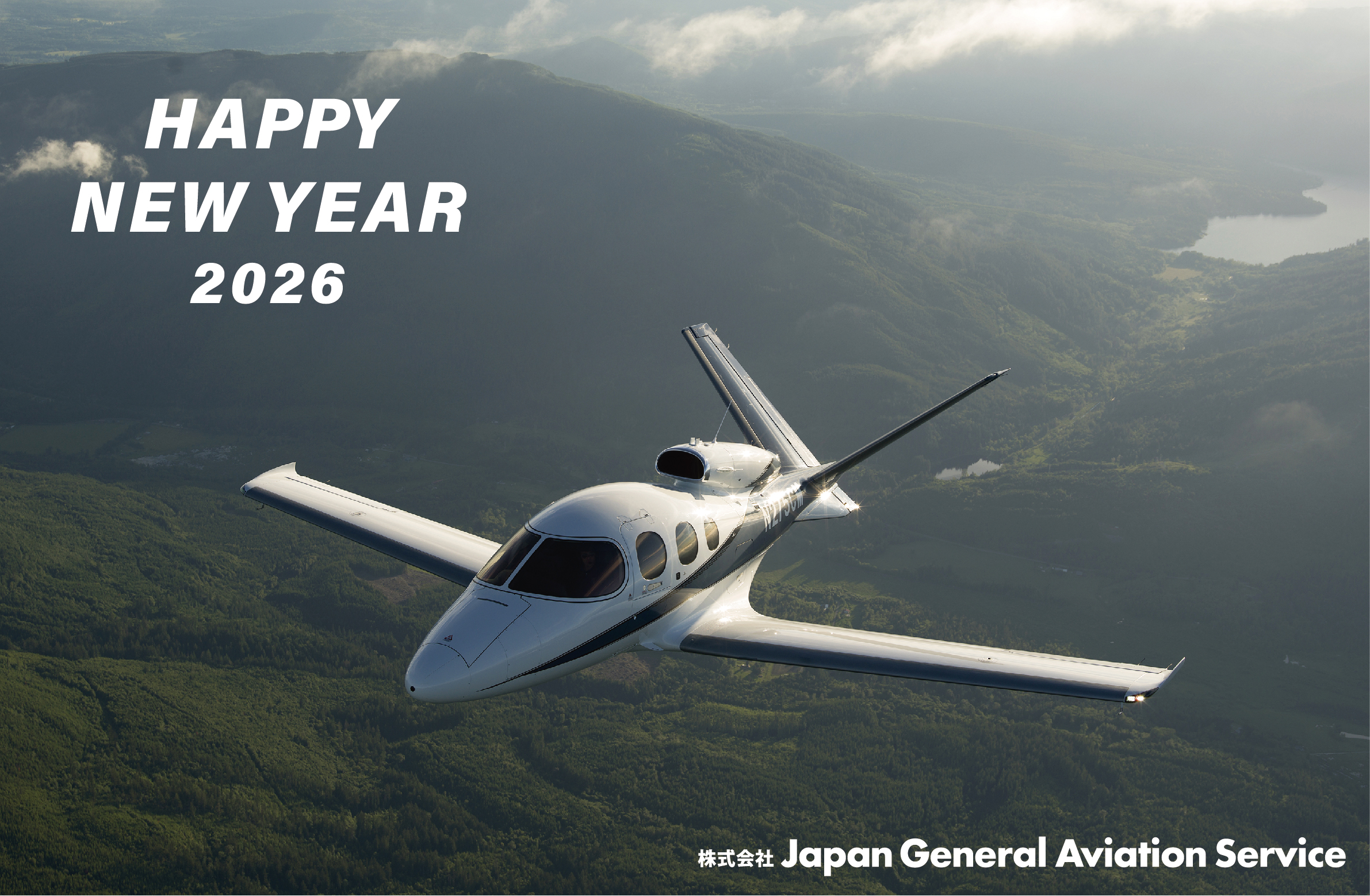さて、いよいよ秋の気配が近づいて来ました。
今回のブログは東京の整備技術部門がご案内します。
先日、鹿児島の整備担当のブログで故障探求について書かせて頂きました。不具合内容によりますが、小型機特有の故障探求の難しさは先のブログで紹介した通りですが、今回は「予防整備」について書かせて頂きます。
航空機は機械モノですから、必ず故障します。
重大なトラブルに陥らないために、航空機のメンテナンスマニュアルでは決められた時間毎に定期点検を行うように定められていたり、使い続けると消耗して壊れてしまう事が分かっている部品は一定時間もしくは一定期間毎に交換するように定められています。これらの定められた交換を予防整備と言います。
他にも、故障の兆候が出た段階(完全に壊れる前)で定められた時間を待たずに交換する事も予防整備と言います。
先日、弊社で予防整備をしていれば・・・という事例がありましたのでご紹介します。
一部の小型機には、エンジンに「Fire Detection Sensor(ファイア ディテクション センサー)」というエンジンに火災が発生した事をコクピットに知らせるためのセンサーがあります。
双発機のエンジンランナップ(エンジン地上試運転)の際に、右側のエンジンが火災を検知したというのです。エンジンを停止して中を見たところ、何も起こっていない。つまり、センサーの誤検知です。
センサーを取り外し、コネクター部をクリーニングして再装着し再度エンジンを回したところ、正常に戻りました。これにて一件落着。
その後、数日、何の不具合も発生せず「やはりコネクター部の汚れか」と皆が考えていました。すると、最初の不具合から1週間たって再び、飛行前点検の地上試運転中に右側エンジンの火災を検知したのです。
今回は、コネクター部をクリーニングしても復旧しません。しかも、飛行機の電源を入れるとエンジンが冷たいのにFire Warningが出ています。
ここから先にブログで紹介された故障探求です。
整備士はセンサーが悪いだろうと目星をつけ、右側エンジンと左側エンジンのセンサーをSWAP(スワップ・相互に入れ替え)しました。
すると、左側エンジンのFire Warningが点灯。明らかなセンサー故障です。
その日のフライトは中止となり、センサーの在庫が無かったため、部品担当はテンヤワンヤ・・・
メーカーに在庫があったため、JGASお家芸?のAOG調達で発注後2日目に部品到着。東京から鹿児島まで航空便で直送しました。
1回目にWarningが出た時に、交換していれば・・・後の祭りです。コネクタークリーニングでOKになってしまうと、「念のため、交換する」とは意外に考えないものです。
採算性と安全性を両立させなければなりませんから、予防整備を実施するか否かの判断はすごく難しい。今回は、会社の判断としてFire Detector Sensorの予備を1個置く事になりました。
これがFire Detection Sensorです。

棒の部分(プルーブ)が熱を感知し、火災発生をお知らせしてくれます。今回の故障では、火災が発生していないのにお知らせしてくれました。
整備技術部門では、日々このような不具合に対処しています。では、みなさん、また次回!