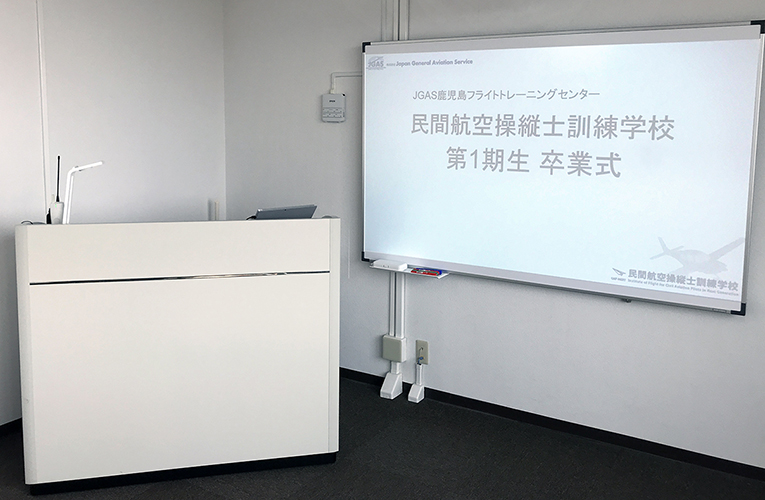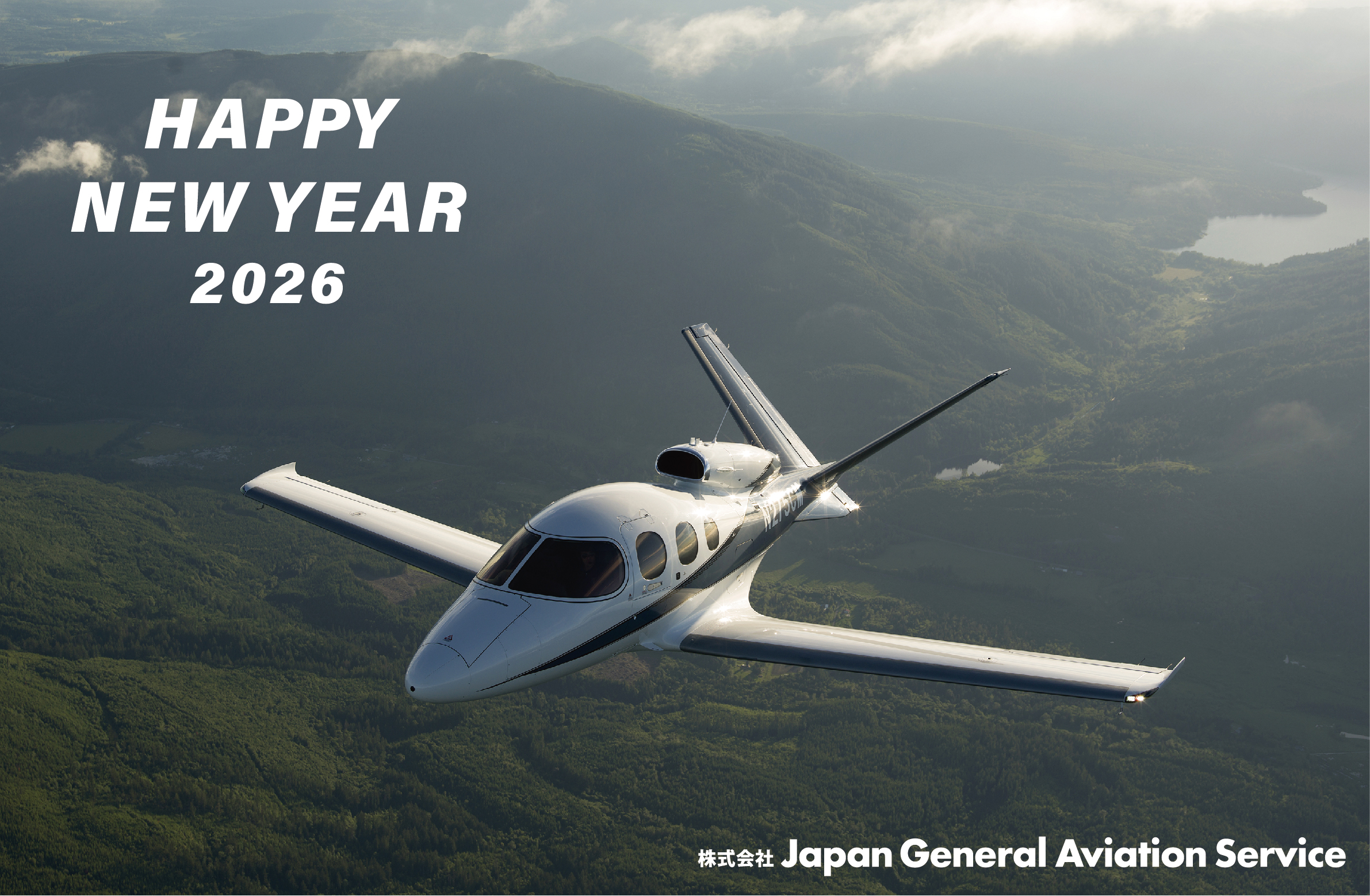いつも当ブログを読んで下さっている皆さん、こんにちは。運航本部長の山口です。
今日は - 航空機を使って事業をする - という意味についてお話しましょう。
航空法第2条(定義)第18項に「航空運送事業」、第21項に「航空機使用事業」が定められていますが、それぞれ「○○とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で~」と前置きがあって
・航空運送事業 : 旅客又は貨物を運送する事業をいう
・航空機使用事業 : 旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう
と定義されています。つまり、簡単に言ってしまえば「旅客又は貨物を運送する事業」以外は、すべて航空機使用事業です。民間航空操縦士訓練学校は「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で」教育訓練を提供しますから、当然、航空機使用事業です。
ここで注意しなければならないのは「航空機を使用して有償で」という部分。無償(タダ)で飛行機に乗せるのであれば事業にはなりません。例えば、無償で遊覧飛行に招待する、などといったイベントなら航空運送事業には当たりません。
また「航空機を使用して」の「航空機」とは、自社機(事業用の航空機)の事ですから、自家用機を所有している方、または航空機をレンタルして飛ばしている方(飛行クラブのクラブ員など)に、教官を派遣して訓練を提供することも航空機使用事業には当たりません(ただし、自社機をレンタルして教官を派遣して訓練を提供するのは、極めてグレーゾーンで限りなく脱法行為に近いと考えられます)。
結局、法に基づいて商売をしようと思えば「(自社できちんと整備をして自社の)航空機を使用して有償で」訓練を提供しなければなりませんから、航空法第123条(航空機使用事業)「航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない」に基づき、航空機使用事業の許可を得る必要があります。
…と、簡単に言っていますが、この許可を得るために考えなければならないこと、決めなくてはならないこと、準備しなければならないこと、は膨大です。
作らなければならない規程類(運航基準や整備基準、訓練規程、安全管理規程、その他の社内規程類)、揃えなければならない設備(飛行機はもちろん格納庫や整備の機材)、雇用すべき人材(航空機乗組員や運航管理担当者、整備従事者)とその訓練など、多くの準備が必要であって、もちろん巨額の費用がかかります。
民間航空操縦士訓練学校の準備は昨年の4月から始めましたから、開校(事業の開始)まで1年半もかかることになります。
加えて、実際の許可申請手続きも大変です。申請書と関連の資料を作成しても、許可が出なければ意味がありませんから、書類の内容に齟齬がないかどうか、実際の体制に問題はないかどうか、などを事前に航空局とも調整し、十分に意思疎通を図って申請に臨まなくてはなりません。
なんでこんなに大変な想いをしなければならないのか、航空局が意地悪をして許可を出したくないのではないか、と勘ぐりたくもなりますが、実際には逆で、むしろ、航空局は積極的に応援してくれています。一緒になって使用事業の立ち上げをやって下さっている。
これにはちゃんと理由があります - それは何か - 経営に関する国籍条項など、様々な理由がありますが、最も大きな要素は…
そう、安全です。
安全を確保して事業を継続できるのかどうか、を審査するのが許可の意味、航空法の精神です。安全を確保するには、一定の設備、人材、お金が要る。安全で調和した運航が可能なのか、運航管理はできるのか、整備の体制に無理はないか、労働環境は適切か、など多くの要素が法に基づき審査され、その審査に合格して初めて事業許可が得られるのです。
これが、航空機を使って事業をする者の、最低限の安全への真摯な態度というもの。
安全はお題目じゃない。念仏のように唱えたところで確保できるもんじゃない。一定の組織体制、一定額のお金、具体的な規程類、社員の正しい行動に基づいて確保できるものなんであって、その審査にすら通らないようでは、安全な教育訓練など提供できるわけがない。どんなに優れた教育ができると豪語したところで、安全を疎かにするのでは意味がないのです。
JGASは航空機使用事業の許可申請を行う予定です。順調に審査が進めば8月にも許可が下りるはずです。ただし、事業許可はあくまでも書類上の審査。それだけでは事業を開始(運航開始)できません。施設検査(正式には「運航管理施設等の検査要領(平成23年6月30日:国空総454号)」による検査)を受けて、これにも合格しなければならないのです。
その予定日が、まさに10月1日。
民間航空操縦士訓練学校の記念すべき開校日が、航空機使用事業者としての事業開始となるのです。ご期待下さい。